本サイトのコンテンツには、プロモーションが含まれています。
空き家がタダでも売れない…義実家の負動産に悩む40代の現実
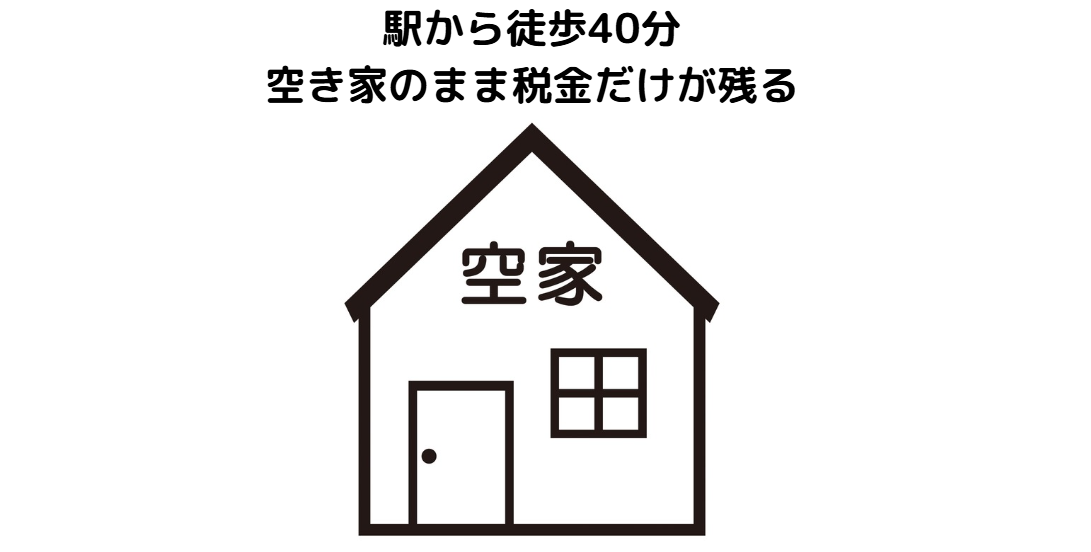

土地を、義実家が持っています。20年以上前に住んでいて、今は引っ越したため空き家です。
今後誰も住む予定もなく、持っているだけ無駄なので、去年から売りに出していますが、全く買い手がつきません。
それもそのはずで、ふるーい団地で、団地内も空き家だらけ。
最寄り駅(電車が1時間に2本)まで徒歩40分。
北向きの暗い場所。更地でなく家付き。小学校の学区でも一番遠い。
近所にはめちゃくちゃ趣味の悪いホテルがドドドーンとかまえています。
そもそも、なーんーでー引っ越しと同時に売りに出さなかったのか…。
旦那には弟がいます。
義弟も既に他県に新築一戸建てを買っていて、その空き家はいらないといっています。
義両親としては子どもたちが将来そこに住むとでも思っていたのだろうか…。
旦那の小学生時代に既に団地内に子どもはおらず、近所の同級生もいなかったほど廃れた地区です。
売れるわけないよ…´д` ;素人の私でもそう思う…。
一度、家付きで買い取ってくれる(二束三文で)という不動産屋さんがいたのですが、旦那が、え~思い出の家、本当に売っちゃうの?
と、訳のわからないことを言い出し、半年ほど引き伸ばしていたら、もう買い取らないと言われてしまいました。
あほかー!!!!!と。叫びたくなりました。
これが実家だったら、私も言いたいこと言いますが、義実家の持ち物だし、旦那はこういったことに私が口を挟むと怒り出すので、何も言えませんorz
いやいや、ほんと、タダでもいいから誰か貰ってくれないのだろうか。
税金だって、義両親いなくなったら誰が払うの?義両親もう若くないよ。空き家のままにもしておけないし、取り壊すのにまたお金がかかるよね。
いやでも、ほんと、これからの日本はこういう土地が溢れるんだろうな…。そしてますます売れない。
手放したい場合、どうしたらいいのでしょうか。
FPとしての解決策|「誰も住まない空き家」をどうすべきか?
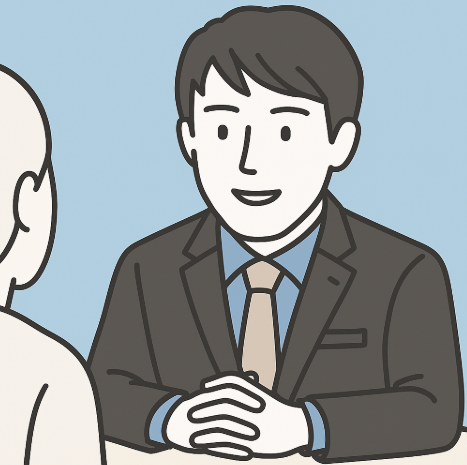
家を売却したいのに全く売れない。このような「負動産」の悩みは、いま全国各地で増え続けています。ご相談のように、
・駅から遠い
・空き家だらけの団地
・建物付き(更地にできない)
・思い出が足かせになって売却のチャンスを逃す
といった複数の要因が重なると、市場での流動性はほとんどなくなります。ここから先は、「誰が、いつ、どんな負担を背負うのか?」を明確にして判断する必要があります。
1.維持管理と固定資産税の「相続後」のリスクを見据える
この空き家をこのまま放置した場合、将来発生するのは以下のようなリスクです。
・固定資産税の支払い(義両親が亡くなればご主人に相続される可能性が高い)
・建物の老朽化による倒壊リスク → 行政指導や罰則(特定空き家)
・解体費用(木造なら100万〜200万円)と整地費用が発生する場合も
・最悪の場合、相続放棄しない限り“誰も使わない”家を抱え続けることになる
放置=問題の先送りであり、むしろ費用と手間が膨らんでいくことを認識する必要があります。
2.思い出より現実。「二束三文」でも早期売却すべき理由
一度あった「家付きで買い取る」という話を逃したのは非常にもったいなかったです。家族の思い出も大切ですが、それが負担になるようでは本末転倒です。
今の段階でまだ買取業者がつく可能性があるなら、金額に過剰な期待をせず、「処分コストが浮いた」と考えることが合理的です。
また、家付きでの売却が難しければ、あえて「無償譲渡」も視野に入れるべきです。条件付きで不動産会社や空き家バンク、地域コミュニティなどに相談してみると、「引き取りたい人」が見つかる可能性もゼロではありません。
3.いま動かないと、将来もっと“身動きが取れなくなる”
所有者が高齢になり、相続が発生してしまうと、処分には「相続登記」や「名義変更」などの手続きが発生し、余計な費用と時間がかかります。
義両親が判断できるうちに「所有者の名義で」動いておくほうが、法的にもスムーズです。早めにイエウールなどの一括査定サービスで複数社から査定を取り、まだ売れる余地があるのか確認しましょう。
不動産の一括査定はこちら(無料)

このような“売れない家”こそ、「時間が最大の敵」です。金額ではなく「次世代にリスクを残さない判断」が大切です。FPとしても、家族の合意を丁寧に進めながら、経済的・心理的負担を最小限にしていくことを強くおすすめします。
みんなのリアルな回答まとめ
私も知りたい。うちの場合は、義家所有のリゾート系マンションの一室。
孫(うちの長男)に、相続させたいそうです。
遺言書に書いたとか…。維持管理費がかかる上、築20年以上。
同じ間取りの部屋が売り出されているのを見たら、数百万なのに買い手付かず。
負の遺産という言葉が、頭の中をぐるぐるしています。
よくよく売れずに固定資産税が負担になるようであれば相続権のある旦那様が相続放棄をすれば済む問題です。
もちろん一銭にもなりませんが負担となる固定資産税に悩まされることはなくなります。
でももし売却もできない、相続放棄もしないとなればやはり実子全員で固定資産税を知らっていくしかありません。
うちはもっとひどいですよ。なんたって、原野&山林ですもん。
売れやしない・・・・(泣)
そして義実家には税金を支払う能力はすでに無く、うちが税金払ってます。うちは最悪、相続放棄も考えてます。
ただただ税金を払うだけの利用価値のない土地なんてお荷物、娘に残す訳にはいきません。親の責任として、どうにか夫の代で縁を切るつもりです。
本当にタダでも良い、イヤ経費はこっちが払うからもらってくれ~~といつも思ってます。
まだ希望がありますよ。もしかしたら、また欲しい人があらわれるかも!
うちは近くに新幹線の線路まで通ってしまったので、再開発などの可能性もゼロとなりました・・・・(泣)
実はうちも義実家系の土地は山奥の田舎で。
いや、いいですよ、別に、だからどうとはおもいません。
不便さもありますが、いいところもあります。でも。
私が、夫が、子供が、将来すむことは絶対にない。
でも、夫は何かの折にちらっと、何かの受け継いだ気持ちとして、多少は相続したい気持ちがあると言いました。(兄弟が何人かいるので、分けることにはなりそう)
あなたはいいよ。私たちの代なら、固定資産税も払おうさ。
でも、子供に、住んだこともない予定もない土地、運用もできる立地条件でもなければ、広さもない土地の固定資産税を払わせることだけはしたくない。
田舎なので、大したことない額ですが、負の遺産だよーーー、と心で叫んでます。
しかし寄付とかもよっぽどのいい土地じゃないと自治体も受け取らないときいたことがあるし、私たちの代でケリをつけるつもりで、子供に残さない努力をせよと、その時が来たら言う覚悟です。
義実家のある集落。小学校はバス登校、車が無いと生活できない。
嫁以外にずーーーと人の出入りが無い土地です。
集落の掟で売ることができないけどそもそも買う人なんていないし。
最近、仕事をリタイアしたご夫婦が集落から便のいい場所に移り住んだけどまだ家があるからという理由で町内の草刈り作業などの参加を求められ欠席のペナルティー(一回1万円が年数回)の支払いを断って地元住民と揉めているらしい。
住んでいなくても祭の会費2万円と祭の寄付金1万円も発生。
義実家は築50年超えで手入れもしていないので人が住まなくなったら朽ちて崩れそう。
旦那は軽く更地にすればいいって言うけど固定資産税が上がりますよね。(今で十数万らしい)
旦那は田舎の長男なので、相続放棄なんて考えは無いしかといって、娘達に遺すわけにもいかない。
私たちの貯金や不動産が残れば相続させたいし義実家のせいで、娘達が自分の親が遺した遺産を放棄するなんてありえない。
どうすれば良いんだろうと考えております。

最終手段は相続放棄なんですね!
もし兄弟ともに相続放棄するとなると、その土地は国?自治体?のものになるということでしょうか。
そもそも地価の安い場所なので、税金は今の所それほど高くはないのですが、私としては使いもしない持ち物を持っていたくない!という思いでして…。
最悪売れなければ、私としては何も貰えなくなってしまうとしても、相続放棄してしまいたいくらいです。娘にまで負担背負わせなくないですし。
いずれにせよ、方法はそれしかないようですね。
空き家どころか、リゾート物件や山林という方もいらっしゃり、すごく大変そうだな、と感じました。(T_T)
あーーー何より口出しできないとろこがストレスたまります!
これが実家の土地なら、自分でさっさと他の不動産屋さんまわったりするのに!
愚痴まで聞いてくださりありがとうございました。
みんなの回答から見えてきたこと|“使わない土地”が抱える切実な現実
回答を寄せてくれた方々の声からは、「想像以上に多くの家庭が“使い道のない義実家の土地”に悩まされている」現実が見えてきます。ただの資産ではなく、“重荷”となった不動産。その実情を、失敗談と学びに分けて整理してみました。
売るタイミングを逃した“後悔”の声
複数の回答者が共通して感じていたのは、「早く動いておけばよかった」という後悔でした。
・一度買い手がいたのに、家族の“情”で売却を先延ばしにしてしまい、その後は買い手がつかない
・「思い出の家だから」と迷っているうちに、老朽化と立地の悪化で価値がさらに下がった
・義両親が健在なうちに整理しておけば、もっと自由に動けたのに…
どのエピソードにも共通するのは、“いつか手放すしかないと分かっていながら、決断ができなかった”というジレンマです。
そして、そのツケは結局、子世代・孫世代にまわされることになります。
相続後に押し寄せる「経済的・心理的な負担」
回答の中には、実際に固定資産税を支払っている方や、法的な選択肢として「相続放棄」まで検討している方もいました。
・「原野と山林」を義実家が所有していて、税金だけを支払い続けている
・リゾート物件を“孫に相続させたい”と言われ、将来の負債を押し付けられそう
・管理費や草刈り費用、祭の寄付など、住んでいなくても義務が発生するコミュニティルール
これらの声から伝わってくるのは、「お金の問題」だけでなく、「口を出しづらい立場」による心理的なストレスの大きさです。
「義実家のことだから言えない」「夫が怒るから何もできない」――
これが自分の親の所有物なら、もっと積極的に動けたはず。“遠慮”が時間を浪費させている現実も見えてきました。
子どもに“負動産”を残さない決意
最後に、多くの方が強く意識していたのは、「この土地を次世代に残してはいけない」という覚悟でした。
・「娘に固定資産税を背負わせたくない」
・「わたしたちの代でけりをつけたい」
・「遺産があるせいで、子が“すべてを放棄”するような事態は避けたい」
思い出も大切、親の気持ちも大切。けれど、それ以上に、「住まない土地」の後始末を誰が担うのか?という問いに向き合う必要があります。
これからの日本では、こうした土地がますます増えていくことが確実です。
「手放したいけど、どう動けばいいかわからない」
「家族の反対があって整理できない」
そんなときこそ、冷静に情報を集め、まずは第三者に相談することが突破口になると、皆さんの声が教えてくれます。
さいごに|FP視点でのまとめ

空き家や使い道のない土地の問題は、今や特定の家庭に限った話ではありません。特に「義実家の不動産」という立場になると、自分の意見が通りにくく、問題が先送りになりやすい構図が見えてきます。
FPの視点から整理すると、このような不動産は「感情」と「お金」が複雑に絡み合う資産」です。そして、“持ち続ける”という判断をする場合には、以下のようなコストとリスクを明確に把握しておく必要があります。
・固定資産税、管理費、修繕費といったランニングコスト
・更地にした場合の解体費や、逆に固定資産税の増加
・地域の掟や自治会費など、居住していなくても発生する費用や義務
つまり、「住まない・貸さない・活用しない」土地は、数字上の価値とは裏腹に、“お金を生み出さない赤字資産”になりやすいというのが実態です。
その上で、次のような方針を早めに決めることが、負の遺産を残さないために重要です。
1. 家族の感情を整理する「話し合い」から始める
「思い出があるから売れない」「将来使うかもしれない」――
こうした言葉が先延ばしを生んでしまいます。まずは、家族が冷静に数字と現実を見つめられるような場を設けることが大切です。
“相続したらどうするか”ではなく、“相続する前にどう動くか”に意識を向けましょう。
2. 売却可能性の有無をプロに相談する
「売れない土地だと思い込んでいたら、意外と買い手が見つかった」
「建物を解体すれば、用途変更で売れた」
こうした事例も少なくありません。
まずは無料で複数の不動産会社に査定を依頼し、現実的な市場価値を把握するのが第一歩です。
不動産一括査定サービスの【イエウール】を使えば、地域の売却実績に強い業者にもまとめて相談できます。
家付き土地でも売却相談できる「イエウール」公式はこちら

3. 最終手段として“相続放棄”を視野に入れる
どうしても処分できず、誰も活用する予定もない土地なら、「相続しない」という選択肢も存在します。
もちろん、それによって他の資産も放棄するリスクがあるため、他の財産とのバランスを見ながらの判断が必要です。
「このままにしておいていいのか」と思った時点が動き出すタイミングです。
義実家の土地や空き家問題は、誰もが避けて通れないテーマになりつつあります。
将来の相続人や家族が困らないように、今できる行動を一つずつ進めていくことが、資産管理における“親の責任”だといえるのではないでしょうか。